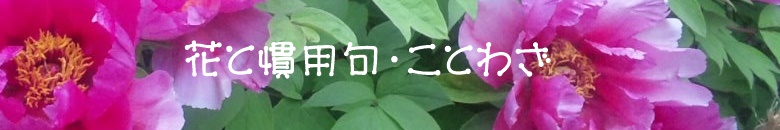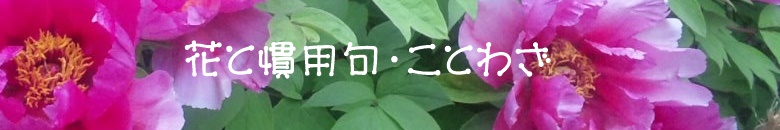| 慣用句とことわざ |
ちょっと解説 |
| 朝顔の花一時 |
朝早く咲き昼には萎んでしまう朝顔の花のように、物事の盛りの時期は短くはかないものであること。 |
| アザミの花も一盛り |
アザミは華やかさに乏しいが、それなりに花を咲かせ美しい時期もある。少女の頃は魅力が乏しいと感じても年頃になれば美しく変わる時期もある。「鬼も十八番茶も出花」も、同じ。 |
| 徒花(あだばな)に実は生(な)らぬ |
徒花は花は咲いても実がならないので、表面だけきれいでも中身が伴わなければ成果は期待できないという意味。 |
| いずれアヤメ(菖蒲)かカキツバタ(杜若) |
どちらもよく似ていて甲乙を付けがたいという意味。 |
| 一葉落ちて天下の秋を知る |
物事のちょっとした前触れから、その後の大勢をいち早く察知すること。 |
| 石に花 |
あり得ないことのたとえで、「石に花咲く」とか、岩に花とか言います。 |
| 言わぬが花 |
差し障りのあることは言わないほうが奥ゆかしいのでは。言わない方がすてきに感じます。 |
| 雨後の筍(うごのたけのこ) |
雨の後筍が続々と生えてくるように次々と物事が現れる様子。 |
| 独活(うど)の大木 |
体が大きいだけで能力も体力もなく役に立たない人をあざける言葉。 |
| 梅に鶯(うぐいす) |
取り合わせの良い、似合っている様子。 |
| 埋もれ木に花が咲く |
世間に忘れられていた不遇の人が、一躍脚光をあび、世に出る様子。 |
| 卯の花 |
ウツギの花のことですが、豆腐の絞りかすである「おから」のことでもあります。 |
| 売り物には花を飾れ |
売りたい品物は美しく飾れと言うこと。婚期にある娘さんに対して言うこともある。 |
| 会に合わぬ花 |
葬儀など大事な行事に飾るべき花が間に合わないとき、役に立たないところから、時期遅れで役に立たないことを言う。 |
| 老い木に花 |
もう花も咲かないだろうと思われる老木に花が咲くことから、衰えたものが再び栄え盛り返すこと。「枯れ木に花」も同じような意味ですね。 |
| 男やもめにウジがわき、女寡(やもめ)に花が咲く |
妻を亡くした男は世話をしてくれる人がいなくなって、家の中や身の回りが汚くなり、一方夫を亡くした女は、自分のことに時間をかけられるようになるため、身ぎれいになってきて、男達からもてはやされるようになる。花が咲いたように華やかになること。 |
| 解語の花 |
人間の言葉がわかる花という意味で、美人のことを称しています。初めは楊貴妃を指していたようです。 |
| 風花(かぜはな) |
初冬に風が立ちちらほら雪が舞うこと。また、晴れた日にどこからか風に送られた雪が舞い降りてくること。 |
| 菫花一日の栄(きんかいちじつのえい) |
菫花とは「むくげ」の花。この世の栄華は、朝咲いて夕方には萎んでしまうむくげの花のようにはかないものであること。 |
| 昨日の花は今日の夢 |
「昨日の襤褸(ランル)、今日の錦」と同じ意味。昨日までは麗しき花のごとくであったものが、今日になってはそれも夢のごときもの。昨日ボロ布をまとっていたものが今日は錦の着物を着ている様を見ると栄枯盛衰は移りやすいものであることをおもわせる。 |
| 錦上花を添える |
錦の上に美しい花を添えておくように、立派なことを重ねること。 |
| 草の花 |
千草の花ともいわれ大変種類が多く、また、小さくて可憐な花が多い。 |
| 喧嘩に花が咲く |
喧嘩がいっそう激しくなる様子。 |
| 黄金花咲く |
万葉集「すろめきの御代栄えむと東なるみちのくの山に黄金花咲く」 |
| 言葉に花が咲く |
話がはずむこと。話がはずみすぎて喧嘩になることもある。 |
| 心の花 |
美しい心、風流を慈しむ心、晴れやかな気持ちなどを花にたとえて言う言葉。同時に花の散りやすいところから、変わりやすい人の心を洗わす意味にも使われる。 |
| 桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿 |
樹木の生育をよくする方法を説いたことわざ。 |
| 三十九じゃもの花じゃもの |
「四十、四十と人は言う、けれど三十九じゃもの花じゃもの。」という俗謡からきたことわざ。まだまだ三十台だからこれから人生の花を咲かせましょう。 |
| 死に花を咲かせる |
立派に死んで死後に誉れを残すこと。死ぬ直後に晴れがましいことがあること。 |
| 死んで花実が咲くものか |
人間死んでしまってはおしまい。どんなにつらくても生きていさえすればいつかは良いこともあると言うこと。 |
| 蕎麦の花も一盛り |
蕎麦の花は地味で目立たないけれども、時期が来れば精一杯に咲いて美しく見えることから、娘は誰でも年頃になると、それなりに魅力が出てきて美しく見えること。 |
| 霜の花 |
庭に降りた霜が美しく絵模様を飾るときがある。そんな状態を示した言葉。 |
| 末摘花(すえつむはな) |
「くれなゐの末摘花の色に出ずとも」と万葉集に詠われます。べにばなの別称です。紅を作るときに紅花の茎の末の花を摘み取ることから末摘花となった。 |
| すべ(め)らぎ(皇)の花 |
牡丹(ボタン)の花のこと |
| 蓼(たで)食う虫も好きずき |
蓼の葉は辛いのだがその葉を好んで食う虫もある。どうも不似合いなカップルとは思っても、人それぞれ好みは人によって違うのですよ。 |
| 高嶺の花 |
唯見ているばかりで手に取ることの出来ないたとえ。 |
| 薪に花(たきぎにはな) |
賤しい姿で粗野であっても、どこかゆかしくて優しい風情のある様子。 |
| 立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花 |
美人の姿を形容する言葉。 |
| 棚から牡丹餅(ぼたもち) |
思いがけない幸運が巡ってくること。あ〜宝くじでも当たらないかな〜 |
| 他人は時の花 |
他人は一時の花のように季節が過ぎれば散ってしまうもので、いつもいつも頼みになるというわけではない。あまり頼りにしてもどうかな? |
| 蝶よ花よ |
娘を慈しみ愛する様子。 |
| 辻が花 |
縫い締め絞りによる絵模様染めのこと。室町から江戸時代にかけて流行したという。女性や子どもの麻布の単衣物に草花模様を紅色に染めたもの。 |
| 月に叢雲(むらくも)、花に風 |
お〜名月じゃワイと見上げれば、雲がかかってしまい、桜の花をと思えば風が吹いている。なんとも思うに任せない様子。 |
| 手活けの花 |
昔芸娼妓を身請けして妻妾とするとき、「手活けの花」という。 |
| 隣の花は赤い |
同じ赤い花でも隣の花は自分の家の花よりも赤くきれいに見えることから、同じものであっても他人が持っているものの方が良いもののような気がする例え。 |
| 十返りの花 |
百年に一度花が咲くという伝説から松の花のこと。祝賀の意に用いられた。 |
| 時の花 |
その時節に咲く花。「時の花をかざす」→時勢に乗って華やかに栄えること。 |
| 常初花(とこはつはな) |
いつも初めて咲く花のように新しく清楚に感じられる様子。 |
| 床花(とこはな) |
遊女と馴染みになってから床の中で与える祝儀の金のこと。 |
| 菜の花 |
アブラナの花のこと。 |
| 主ある花 |
決まった男のある若い女性のこと。 |
| 寝て花やろ |
麹を室の中に寝かしておくと麹黴(こうじかび)が咲くことから、寝て待っていれば良いことがある、「寝て楽しむ」「楽しい夢を見る」という意味になる。 |
| 花一時、人一盛り(はないっとき、ひとひとさかり) |
花が美しく咲き栄えるのも僅かに数日間のこと、人も栄えるのは僅かな時期にすぎないということ。 |
| 花に嵐 |
花が咲くと激しい嵐が吹いて花を散らしてしまうことから、良いことにはとかく邪魔が入りがちであること。 |
| 花盗人(はなぬすびと)は風流のうち |
花の美しさに惹かれて、つい花の枝を折ってしまうことがあるが、花の美しさに惹かれたあまりのことであるので、風流心の表れであるから、あまりとがめ立てをしないということ。花盗人のいいわけだ。 |
| 花は折りたし梢は高し |
ほしいけれども手に入れる方法が見つからないこと |
| 花は桜木、人は武士 |
花では桜が、人では武士が最も優れていると言うこと。(本当かね?) |
| 花は根に、鳥は古巣に |
経過はいろいろあっても、最後は元に返ると言うこと。 |
| 花も実もある |
木や枝には、美しい花だけではなく実を付けることから、外見だけではなく中身も充実していること。また、道理も人情もわきまえた処理の仕方を言う。 |
| 花も恥じらう |
花さえも引け目を感じるほど若い女性のみずみずしい美しさの様子を表す。花も恥じらう17歳。 |
| 花より団子 |
風流なことより実益を、外観よりは内容を重視する例え。 |
| 花を持たせる |
相手を立てる。相手に名誉や栄光を譲る。 |
| 初花 |
17,8歳くらいの女の子。または、その季節になって初めて咲く花を言う。 |
| 一花咲かす |
一時的でもいいから栄華を得、賞賛を得ること。 |
| 不香の花(ふきょうのはな) |
すなわちニオイのしない花、雪のことである。 |
| 坊主の花簪(はなかんざし) |
髪のない坊主に花簪は必要がないことから、似つかわしくないものの例え。持っていても役に立たないことの例え。 |
| 増花(ますはな) |
前の女よりも愛せる女。失恋した男に「また増花もあるから」と慰めるとき。 |
| 待つうちが花 |
物事は、結果はどうなるだろうと待っている間が楽しいということ。 |
| 水の花 |
池や沼の表面に植物プランクトンが大量に発生して水面に浮く現象。 |
| 見ぬが花 |
物事は実際に見ないであれこれ想像しているのが楽しい。 |
| 六日の菖蒲、十日の菊 |
五月六日の菖蒲では五月五日の端午の節句に間に合わず、9月10日の菊では、九月九日の重陽(ちょうよう)の節句に遅れてしまい役に立たないことから、時期に遅れてしまうと、役に立たないつまらないものになってしまう例え。 |
| 六つの花(むつのはな) |
六角形の結晶である雪のことを指す。 |
| 物言う花 |
美女のこと。 |
| 物言わぬ花 |
自然の普通の花 |
| やはり野におけ蓮華草(れんげそう) |
蓮華草は野原に咲いているときが一番美しいのであって、摘んでしまえば意味がない。物事には相等しい場所や時があるのであって人にもその人にあった環境が一番よろしいと言うこと。 |
| 闇に咲く花 |
夜街角に立つ女。街娼 |
| 木綿花(ゆうはな) |
木綿で作った白い造花のこと。昔女性の髪飾りとなった。 |
| 雪の花 |
雪が降るのを花が散ることにたとえられた。 |
| 湯の花 |
温泉の中から生じてくる沈殿物を言う。 |
| 宿花(よみはな) |
返り咲きの花。一度咲いた後、二度咲きする花。 |
| 落花流水の情 |
落ちる花は流れる水に身を任せ、また、流れる水は落ちた花をいつまでも浮かべたまま流れてゆきたいという気持ちから、男女が自然に身を寄せ合うようになることの例え。 |
| 両手に花 |
二つの良いもの、美しいものを一人で持ってしまうこと。 |